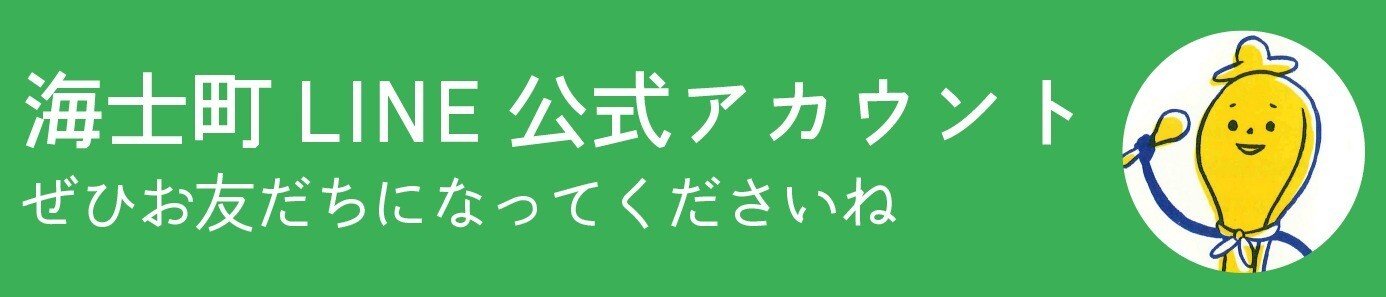【海士町で初めての離島暮らし】本氣米の課題解決に取り組むJICA海外協力隊実習生
JICAグローカルプログラム実習生として海士町で活動していた芝野雄大(しばの ゆうた)さん。12月にグローカルプログラムの任期を終えて、JICA海外協力隊としてコミュニティ開発でエルサルバドルに派遣予定です。芝野さんの今までの経歴を掘り起こしつつ、海士町での活動の様子を取材しました。
JICAグローカルプログラムとは
JICA 海外協力隊のうち帰国後も日本国内の地域が抱える課題解決に取り組む意思を有する希望者を対象に、自治体等が実施する地域活性化、地方創生等の取り組みに2ヶ月半OJTとして参加できるプログラムです。
JICA海外協力隊に応募するまでの経緯を教えてください
小学生の頃から「海外で仕事をしたい」というのは頭の中にありました。昔、カンボジアの小学校にブランコを作る団体の本を読んだんです。日本でブランコというのは当たり前の存在。でも、カンボジアの小学生たちはすごく喜んでいて。ブランコひとつで小学生を笑顔にできる。なんて素晴らしいんだろうと思いました。
開発途上国の暮らしはわからないけど、先進国の日本で生まれた自分だからこそ、自分の力で少しでも世界を良くできたらいいなって思った。それが国際協力に興味関心を持ったきっかけです。英語の勉強も好きだったというのも理由のひとつです。これを頑張れば世界で働けるだろうと思いながら勉強していました。
そんななかで、高校の時に海外大学進学クラスに入りました。卒業したら海外の大学に進学できるようなカリキュラムが組まれているクラスで、国際交流が盛んなところでした。
高校卒業後は、イギリスの大学に進学しました。英語を勉強していたとはいえ、やはりイギリスの生活は大変でした。海外に住むのも初めてだし、周りの学生も言語の面だけではなく、勉学へのモチベーションや頭のキレの違いにショックを受けてしまったんです。周りに優秀な人たちがたくさんいるなかで、自分にできることは何もないんじゃないかと思った時期もありました。

大学卒業後、何をしようかと考えたときに「海外の人ともっと関わりたい」という思いがあり東京の日本語学校に就職しました。日本語学校で4年ほど働いた時に、実は一度JICA海外協力隊に応募して合格をいただいていたんです。日本語学校を退職して、さあ海外に行こうと思った時にコロナ禍になってしまって。一度協力隊の夢は諦めないといけませんでした。
JICA海外協力隊になりたいというのは頭の隅に残ったまま、もともと働いていた日本語学校にそのまま残ることにしました。合計8年半務めましたね。コロナが落ち着いたタイミングで、YouTubeの広告か電車の吊り広告かわからないですけど協力隊の募集をしているのを見て「もう募集やってるんだ」と思った記憶があります。その思いのまま応募し合格をいただいて今に至ります。
JICA海外協力隊の派遣地は希望通りでしたか?
コミュニティ開発でエルサルバドルに派遣予定なのですが、実は第一希望です。海外で働きたいと思った時に、国連をはじめとする国際機関の職員や外交官もかっこいいと思っていました。国連の公用語の中にはフランス語やアラビア語もあってどれにしようか迷いましたが、世界で話者が多いのはスペイン語なのでスペイン語の習得に興味関心がありました。なので大学の選択科目や社会人の公開講座でスペイン語を少し勉強していたんです。でも、どうしても断片的な学習になってしまっていて。ちゃんと身につけたいなという気持ちもあったので派遣先がスペイン語圏というのは一応希望として持っていました。
そのなかで、エルサルバドルのコミュニティ開発はスペイン語圏でありながら、要請内容がすごく魅力的だったんです。

なぜグローカルプログラムに?
一度コロナ禍の時期にJICA海外協力隊に合格した時はグローカルプログラムといのはなかったんですが、もう一度応募して合格をいただいた時に、グローカルプログラムのお知らせが来ました。前回はなかったものだから気になったんですよね。
ずっと都会でしか暮らしたことがなかったので、地方に行ってみると新しい経験とか発見があるんじゃないかと思って参加しました。また、現地に派遣されたときに必ず役に立つだろうと思ったのも理由のひとつですね。
たくさん候補地があるなかで、なぜ海士町に?
先ほども言いましたが、ずっと都会でしか暮らしたことしかなかったんです。田舎暮らしをしたこともないし想像したことすらもなかった。そんな僕には、離島っていうキーワードがすごく魅力的で。離島だからこその暮らしは、僕にとってなんでも新鮮にうつると思いました。
あとは海士町の掲げる「ないものはない」というキャッチフレーズも魅力的でした。なんでもある都会に暮らしていた自分にとって、「ないものはない」生活ってなんだろうと関心が湧いたんです。今回こないと今後も田舎暮らしは経験することがないかもしれないと思い、思い切って海士町を選びました。

海士町に来る前と来た後での心境の変化は?
実は海士町に来るときに、敢えて事前情報をそこまで調べずに来ました。なので「思っていたのと違った!」みたいな経験はないですね。
しいて言えば、海士町にきてからのんびりできているかなと思っています。東京にいるときは退職も重なっていたのですごくバタバタしていて。あの生活に比べると、島での暮らしはのんびりしていますね。
あとは、「人とのつながり」を感じる瞬間が多いです。僕の地元は人こそたくさんいるけど顔を知らない人ばっかりです。近所の人とか職場の人とか決まった人としか関わりがないので。
でも、この島の人たちは人と人とが密につながっている。食材を買いに商店に行っても、お客さんたちはみんな知り合い同士。名前を出すと「あの人ね」と一発でわかります。島内の人々の団結や交流を深めるきっかけも多い。11月は特に祭りやイベントが多いので、練習や準備の時間を通して人と知り合う機会はすごく多かったです。プライベートで繋がった人が、実は取引先の人だったとかもあります。自然体でいられる人にとってはすごく住みやすい場所だなと思っています。
現在の活動とそこにした理由を教えてください
海士町のブランド米で本氣米というものがあり、海士町役場 地産地商課に所属し本氣米プロジェクトの振興に関わっています。具体的には本氣米の課題解決、広報やイベントのお手伝いも行っています。特に11月はイベントが立て続けにあるので、今はイベント準備のお手伝いや企画関係が多いですね。
海士町のグローカルプログラムでは、来島して1週間は研修という形で活動先の候補地をまわるんです。いくつかある候補地の中から最終日に自分で活動先を選択するんですが、最終日までどこにするか、何がやりたいか実はかなり悩んでいました。
本氣米プロジェクトでは、米の生産者、それをプロデュースする側の役場の方とどちらもお話をお聞きしました。そこで感じたのが、生産者と役場の人の見ている方向が少し違うなって思ったんです。そこがなんだろうと純粋に気になって、もっと知りたいと思いました。どちらの考えも知らないといけないし、折り合いがつく部分とつかない部分があるとは思いますが、これからの活動を通して知りたいと思っている部分です。


活動先を海士町役場 地産地商課に決定
活動を通して難しいと思っている部分は?
米の生産者との時間がなかなか持てないところですかね。
今住んでいるのは日須賀地区という場所にあるシェアハウスなんですが電波がなかなか通じないんです(笑)生産者のところに行くには前もってアポイントメントを取って行きたいのですが、電波が通じないのでなかなか約束できない。難しいところです。ですが、自分発信で何かイベントもやりたいと思っているので、もっと生産者と関われるように動いていきたいと思っています。
活動を通して心がけていることは?
海士町では週末たくさんのイベントがあるんですが、気になるものがあれば積極的に参加するように心がけています。前にあったのは、気になっていた高校のイベントに参加した時に仲良くなった人が、実は別の活動の時にお邪魔したところの職員さんで盛り上がりました。
他には昔から剣道をやっているという特技を活かして、海士町の剣道クラブに先生として通っています。先生として剣道と関わると視点が変わっておもしろいですね。子どもたちと触れ合う良い機会にもなっています。

グローカルプログラムで海士町にいるので離島日は既に決まっていて、これからエルサルバドルでの生活が待っています。地域のイベントが地域を結ぶ・人を結ぶということを実感できたので、任地にいっても地域の行事活動には積極的に参加したいと思っています。

活動期間の半ばでの振り返りと気づきを町民の方へ発表する
(芝野さんは右から2番目)
グローカルプログラムの参加を迷っている人へ一言
迷っているなら1回海士町に来てみるといいと思います!
特に都会で暮らしている人。あえて全く育った環境とは違ったところに行ってみるのはいい経験だと思います。海士町は人と人とが繋がって、お互い支え合っているようなイメージなので、人との繋がりを感じられる場所だと思います。
今回は芝野雄大さんにお話をお伺いしました。次は同じくグローカルプログラム実習生で活動している小尾さんにお話を伺います。
お知らせ
島根県隠岐郡海士町にはJICA海外協力隊経験者が9名(2025年1月時点)在住しており、開発途上国での隊員経験を活かしながら教員や役場職員等として海士町の地域活性化に貢献しています。この度、海士町に在住する3名の隊員経験者にインタビューを行いました。JICA海外協力隊としての海外経験が帰国後の日本地域でどう活かされているか、また協力隊の活動を含むキャリアパスなどを是非ご覧ください!
インタビュー動画はこちらから👇
日本の地域で活躍するJICA海外協力隊経験者へのインタビュー ~本編~