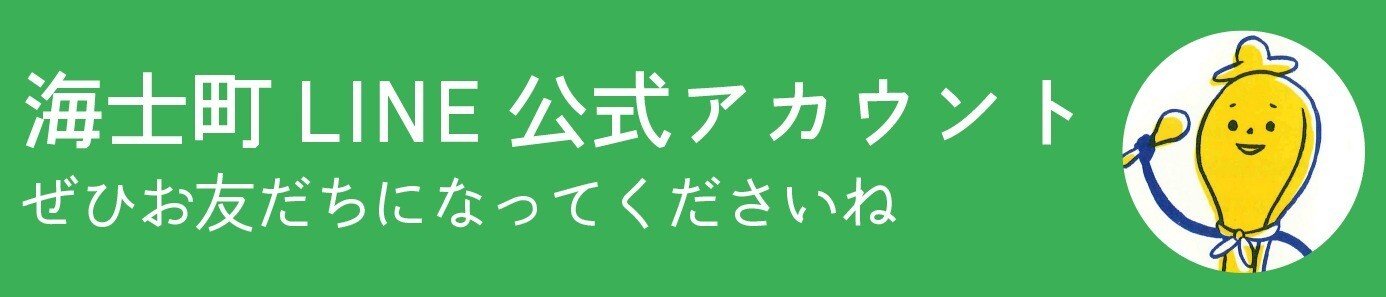後鳥羽院遷幸八百年記念文化祭レポート「つながる800」
令和3年10月16日(土)に、後鳥羽院遷幸八百年記念大祭が隠岐神社で斎行されました。大祭後は記念奉納行事として、さまざまなプログラムが用意されていました。今回はその様子をレポートしたいと思います!

記念奉納行事プログラム
10:00~ 後鳥羽院遷幸八百年記念大祭
13:00~ 100万人のクラシックライブ
14:00~ お山の教室
14:10~ かわず太鼓
14:30~ こころ音雅楽会
15:30~ 学習発表会(福井小学校)
15:45~ 白拍子舞
16:00~ 隠岐島前神楽
17:00~ キンニャモニャ
18:00~ 奉納刀神前打初式(月山貞利氏)
18:30~ お餅抽選会
当日は、あいにくの雨の中での開催となりました。後鳥羽上皇に関するお祭りは雨の天候になることが多いそう。
また、島根県知事の丸山知事や、刀剣研究家のポール・マーティンさんなど、島外のみなさんにもお越しいただき、節目の八百年に相応しい行事になったのではないかと思います。

後鳥羽院遷幸八百年記念 神殿祭

神殿祭では、修祓(しゅばつ)や、献饌(けんせん)、祝詞奏上などを行いました。また吟詠奉納では、隠岐島前高校の元教員で吟士でもある石橋さんが、君が代と御製歌を吟じられました。

昨日の午前中の隠岐神社の祭典で、詩吟の先生(石橋縁岳さん)が神前で吟じていたようす。この時間帯は神社にあがれず聴けなかったけど、神門で受付をしていた方が遠くから撮影してくださいました。嬉しい😂
— 隠岐後鳥羽院大賞 (@welcomegotoba) October 16, 2021
聴こえるかなあ。 pic.twitter.com/4yFCZOJnNW
修祓:神道の儀式で、穢れや災いなどを祓い清めること。
献饌:神前にそなえ物をすること。
また、海士町にある福井小学校・海士小学校6年生の4名が、後鳥羽上皇が詠んだ和歌「我こそは 新島守よ 隠岐の海の 荒き波風 心して吹け」に独自の曲と振りを付けた「承久楽」を奉納しました。


100万人のクラシックライブ

神殿祭後は後鳥羽上皇遷幸八百年の記念公演です。トップバッターは100万人のクラシックライブでした。
このクラシックライブは、全国各地で年間100万人のみなさんの参加を目標とし、クラシックに馴染みのない方たちにも生の演奏の素晴らしさを感じてほしいという思いから、様々な場所で演奏をされているそうです。



愛のあいさつや、炎(鬼滅の刃)、海士町民の歌、情熱大陸など、アンコールを含む全9曲を披露していただきました。
特に印象的だったのは竹取物語。終盤ではかぐや姫が月に帰る心境が表れているような悲しみが伝わる音色でした。
お山の教室

NPO法人 隠岐しぜんむらが運営する「お山の教室」は、晴れの日はもちろん雨や雪の日も自然の中で過ごす『森のようちえん』スタイルの保育を海士町でされています。
神門にはお山の教室で作られた作品が飾られていました。


ドングリや木の板を使用してケーキや電車に見立てていたり、枯葉に色を塗るなど、かわいくデザインされていました。
かわず太鼓

かわず会は、海士町の様々な地区の幅広い年齢層のみなさんによって構成されている和太鼓のグループです。総勢11名で「三宅」という曲を披露していただきました。
「三宅」は動きに緩急をつけるという特徴があるそう。雨と寒さを吹き飛ばすような迫力ある演奏でした。


毎週火曜日に島民ホールで練習を行っているので、海士町にお住まいのみなさんはぜひ見に来てくださいとのこと。毎年8月に海士町で開催されるキンニャモニャ祭りなどでも披露されており、翌月の産業文化祭でも披露されるそうです。
こころ音雅楽会

雅楽とは、1200年以上の歴史を持ち、日本の古典音楽として、仏教伝来の飛鳥時代から平安時代初めの間に、中国大陸や朝鮮半島から伝えられた音楽や舞、平安時代に日本独自の様式に整えられた音楽のことです。


管絃と舞楽の2種類を演奏されました。
管絃では、笙(しょう)や、篳篥(ひちりき)、琵琶、筝(そう)、太鼓などの楽器を使用し、平調・越殿楽や今様越殿楽、太食調・越殿楽を披露されました。



舞楽では、雅楽の楽曲を伴奏の中、「陵王」という舞いを披露されました。
後鳥羽上皇の時代にあったとされる伝統的な雅楽を、800年たった今も味わえる特別な舞台でした。


学習発表会(福井小学校)

海士町に2つある小学校の1つ、福井小学校民謡クラブの5・6年生と先生方11人のみなさんが新海士町音頭を披露しました。
昔から海士町民に愛されている新海士町音頭を子どもたちに継承していく姿をみて、もっと伝統を大切にしていきたいと感じる舞台でした。

こちらも、来月の11月に行われる産業文化祭などでも披露予定だそうです。
白拍子舞

白拍子(しらびょうし)は、男装した遊女が今様や朗詠を歌いながら舞を披露する歌舞の一種です。
後鳥羽上皇が寵愛した亀菊という女性は元白拍子だったこともあり、後鳥羽上皇と縁が深い慈円が作詞したとされる越天楽今様の曲に合わせて、舞いを披露していただきました。


隠岐島前神楽

隠岐島前神楽保存会のみなさんに、隠岐島前神楽を披露していただきました。隠岐神楽のうちでも島前の三島で行われている神楽を島前神楽といいます。
演目は、幣帛舞(ぬさまい)と湯立(ゆだて)でした。湯立は海士町では初披露だそうです。



▼隠岐島前神楽に興味のある方はぜひこちらもご覧ください!
キンニャモニャ

3か月のインターンシップ制度で海士町に滞在している島体験生がキンニャモニャ踊りを披露しました。11人の島体験生は今年の10月上旬に来島しました。


もちろんキンニャモニャを踊るのは初舞台。地元のみなさんに教えていただきながら、練習を重ねたそうです。三味線や太鼓の地方(ぢかた)さんの生演奏もあり、地元の方も、移住された方も、色々な人とのつながりを感じる発表会だったと思います。
奉納刀神前打初式(月山貞利氏)

後鳥羽上皇は日本刀への造詣が深く、自ら作刀も手掛け「御番鍛冶」制度をつくられました。
後鳥羽院遷幸八百年奉納行事の目玉の一つでもある奉納刀神前打初式では、修祓や火種献上、玉串拝礼などを行い、火種献上では、御神火と奉納刀を作る際に使用する「玉鋼」(たまはがね)を神前に献上しました。




奉納刀神前打ちは、奈良県指定無形文化財を保持され、全日本刀匠会顧問も務められる月山貞利氏によって奉納刀神前打ち初めが行われました。
火入れという作業では、座高ほどの高さの火をおこし、その火の中で島根県内で産出された玉鋼を熱して形を整えていきます。記念槌入れでは、丸山知事や海士町長などが槌入れを行いました。
▼刀剣の作り方




新御番鍛冶プロジェクト
「新御番鍛冶プロジェクト」は、御番鍛冶の伝承を現代に甦らせ、後鳥羽上皇をまつる隠岐神社に現代最高峰の刀工技術で作る刀を奉納することで、刀剣文化を記憶、そして次の世代に継承してゆくことを目指しています。
新御番鍛冶に相応しい刀匠12名が刀の奉納を行うとのこと。Makuakeというサイトで2022年01月12日までクラウドファンディングをしています。プロジェクトに共感してくださった方は、ぜひ応援していただけるとうれしいです。
お餅抽選会

あいにくの天気だったため、餅投げはお餅抽選会となりました。小中学生や高校生の代表、島根県知事、町長等がクジを引き、当選した方には銭餅が配られました。

終わったのは19:00頃。夜の隠岐神社は風情がありました。みなさんと海士町の文化や日本の文化を改めて感じることができ、これからも伝統を残していかなければと思う記念祭だったのではないかと思います。
後鳥羽院遷幸八百800年記念文化祭は本日限りですが、隠岐神社に来られ際にはぜひ、いつもよりゆっくり歩いていただき、のんびり気分を味わいながら悠久の歴史に思いを馳せてみてくださいね。
▼後鳥羽院遷幸800年のホームページ
[文:嘉根(大人の島留学生)]