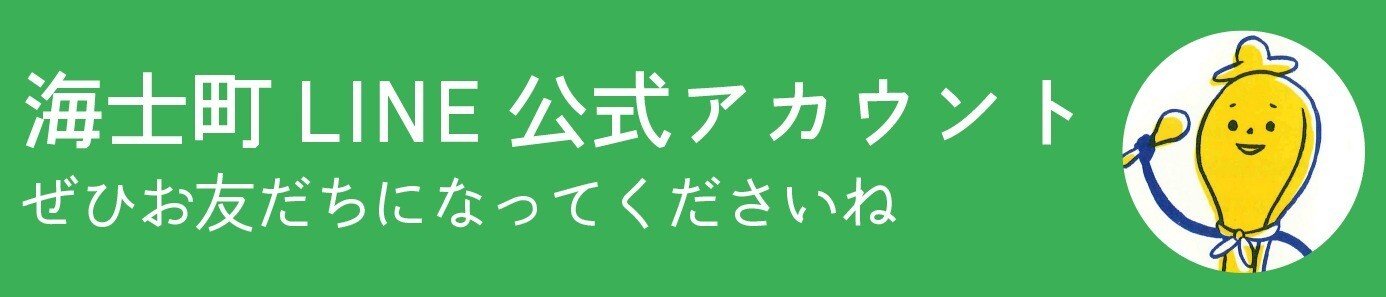手仕事でつむぐ、海士町の伝統菓子「白浪」。
みなさん「白浪」はご存じですか?
白浪とは、海士町のおみやげとしても知られ、長きにわたって親しまれてきた伝統的な和菓子です。

「白浪」という名の通り、白く、あんことお砂糖の甘さが広がります。
島内のお店や家庭でも作られていましたが、約70年前に常盤堂製菓舗で「白浪」と名付け商品化。現在は、海士町のお土産と手仕事のお店「つなかけ」さんでその製法と味を守り、伝統を引き継いでいます。
昨年、パッケージやロゴも新たにリニューアルされました。

むかし遠流の身となられた貴人たちをお慰めしようと もち米をいり粉にして、小豆をたき、お菓子とみなして献上したものが「白浪」のモチーフになっているのだとか…
一本一本、手作業でつくられているという「白浪」。
みたことや食べたことはあるけどどうやって作られているのでしょうか?
今回、後鳥羽上皇ゆかりの伝統文化を子どもたちに体験してもらう教室「ごとばんさん伝統文化未来教室」で「白浪」づくりが行われるということで海士町noteスタッフも行ってきました。

講師は「つなかけ」さんで白浪の製造にも携わっている濱家さんに教えていただきます。

「白浪知っている人―!」と聞くと、「給食にでてきたー!」と子どもたちにも人気の白浪。

では、白浪って何でつくられているのでしょう?
「米粉、砂糖、片栗粉??」
白といえばの食材がたくさん出てきました。

正解は、もち米を蒸して、白く焼いたあとサラサラの粉末状にした「寒梅粉」。それと上白糖がベースになっているといいます。

上白糖だけだと寒梅粉がくっつかないため、お水を加えますが、季節によって気温や湿度が異なり、お水の量も変わるといいます。
繊細な白浪は長年の経験がないと感覚が身に付かないと講師の濱家さんは話します。ちなみに、1日400本、1年間に2万本も製造しているそうです。

濱家さんにレクチャーいただいたあとは、いよいよ白浪作りのスタートです!

木枠に砂糖と寒梅粉を混ぜた粉をいれる。

あんこを細長くしてつめる。

あんこを隠しながら、木枠からは粉がこぼれないように薄く敷き詰めたら…

ひっくり返す!!!
半円柱で海の波を彷彿させるこの模様。白浪の完成です!!

よくみるとこの形、何かに似ていませんか?昔は、島内で「かまぼこ」と呼ばれていたとか…。

気づけば、いろんなかたちの白浪がトレーにびっしり!!
みんなでたくさんつくりました。

最後は、さくら茶と一緒に白浪をいただきます。

はじめて食べる出来たての白浪は、ふわっとほろっとした触感。
ほどよい甘さが、塩味のあるさくら茶とぴったりでした。

「ふわふわしてて美味しかった!」、「崩さないようにつくるのが大変だった!」という感想とともに海士町の伝統ある和菓子を味わいました。

一本一本手作業で、大切に受け継がれている白浪。
ぜひ、みつけたら食べてみてくださいね。
(海士町noteスタッフ:渋谷)