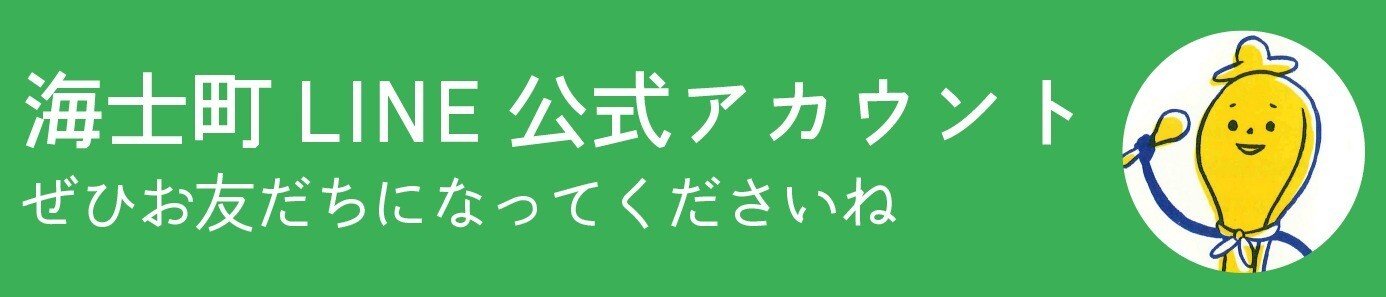普段は見れない?海士町民具館の漁具展へ!
海士町民具館。
なんと、期間限定で昔の漁具を展示しているということで、noteスタッフもいってみました。

漁具といったら、釣り竿とか漁網とかかな?
そんなイメージを膨らませながら、お邪魔します!

中に入ると、「あれ?これが漁具なの!?」
どれも、見たことない道具ばかりです。

今回、この展示会を企画したのは、JICA海外協力隊グローカルプログラム生として来島した、林さん。
海外に派遣される前の2ヶ月、海士町観光協会と教育委員会伝承郷育係に所属し、地域に入って活動しています。

今回は、そんな林さんの案内のもと、昔の漁具の世界にいってみましょう!
noteスタッフ:
早速ですが、この穴の開いた筒は何ですか?

林さん:
これは、筌といって魚の習性をいかして捕獲する道具です。筒の中にエサを入れて、水中に沈めて魚を獲ります。
魚がこの筌に一度入ると出られない仕組みになっているみたいです。

noteスタッフ:
大きい巻きすのようなものも、漁具なんですか?

林さん:
これは海苔簀という岩海苔を持ってきて乾かす道具で、乾海苔にするためのものですね。冬場に行われる作業みたいですよ。

林さん:
漁師さんの暮らしをとり上げた「あまのききがき」という本にも載っています。
図書館の方とも協力して、関連する本も置いてみました。
noteスタッフ:
本を読みながら展示をみると昔の漁のやり方や漁具の使い方など、より理解が深まりますね。

林さん:
この道具も面白いですよ!
棒の先に釣り糸を垂らして使う「はんじき」という道具です。
船の上からイカ釣りに使われていました。
もともと一本で釣っていたみたいですが、一本だとイカの量が取れないから、両手に一本ずつもって二刀流でイカを釣っていたらしいです(笑)
noteスタッフ:
二刀流ですか⁉使いこなせると人間の技術も進歩するものですね。

noteスタッフ:
蛸壺もありますね!

現在ではコンクリート製のものを用いて、カニを餌にしておびき寄せ、タコが入ると蓋が閉まる仕組みになっているとか。
林さんお手製の説明書きは、過去と現在の民具の違いも楽しめます。

林さん:
これは、水中を覗きながら獲物を狙う箱眼鏡です。
形状は違いますが、現代でも用いられるときがありますよね。
noteスタッフ:
木製なところが歴史を感じます。

noteスタッフ:
そんな箱眼鏡の横には、海鼠落とし??
なんだか、名前も不気味ですね(笑)

その名の通り、こちらはナマコを狙う道具。
箱眼鏡で水中を覗き、ナマコを見つけたら、このかえしのついた鋭い道具を上から落として仕留めるとか。

林さん:
箱眼鏡は東北とかでも使われているみたいですが、海鼠落としは、調べてもあまり文献が出てこなくて、島根の民具としては出てくるので、もしかしたらこの辺だけなのかな?
ぜひ、持ってもらえるとわかると思いますが、すごく重たいんですよ!
見に来られていた方も、片手では持ち上げられない重さにびっくり!!
「筋トレで使えそう(笑)」

現在のナマコ漁は、網ですくいあげる方法が主流だといいます。
「昔の方はこんなに重い道具で漁をしていたのか~」
そんな苦労も実際に触れることで実感することができました。
林さん:
実は、この漁具たちは一般公開されている民具館ではなくて、隣にある新民具館(普段は解放されていない)に置いてあったんです。
普段はみれないからこそ、みなさんに興味を持ってもらえるんじゃないかなと思って展示しました。

林さん:
海士町は漁業も盛んなので、昔の漁を知ってもらえたらいいなと思います。
そして、島民のみなさんにも、民具館という場所を知ってもらえるきっかけになったら嬉しいです。
▼こんな素敵な民具たちも楽しめます。

漁具が見れるのは、7/10(水)まで!
ぜひ、昔の道具を体感してみてくださいね。
(海士町note担当:渋谷)