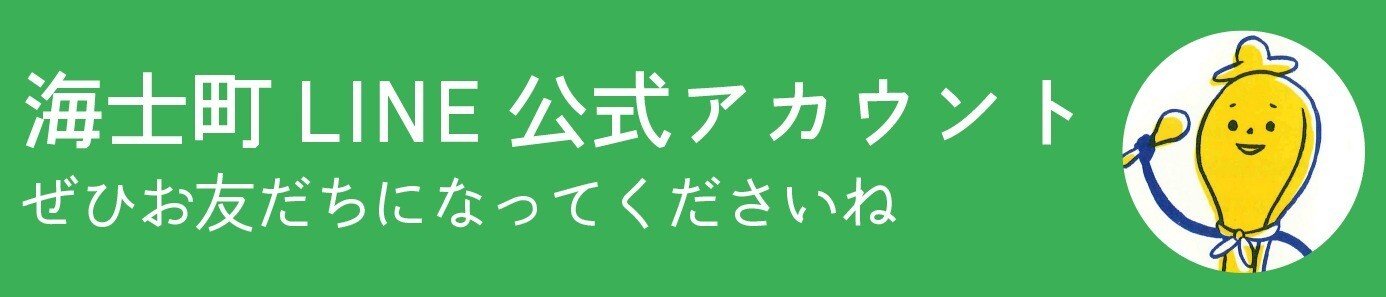通学合宿が行われました
月日の流れは早く、今年最後の月となりましたが、9月に引き続き10月には小学四年生の宿泊体験である通学合宿!海士町にある2校の小学校(福井小学校と海士小学校)の子どもたちが参加しました。

通学合宿とは
公共施設利用時や集団生活時におけるマナーを身につけ、集団生活を通じて、協力して行動する力を伸ばすと共に自立心を高める。
自分のことは自分でする”自立”・めざせ!ふるまい名人”挑戦”・つながりを深める”交流”の力を身につけよう!という。子どもたちには、分かり易いように5つの名人を目指してがんばってもらいました。

また、今回の宿泊合宿は小学4年生対象ということもあり、9月末に開催された普段の生活学校とは趣旨が異なります。”普段の生活学校”ではより生活技術と集団生活を学ぶために行われましたが、今回の”通学合宿”では集団生活時におけるマナーを身につけることに重点が置かれました。
お母さんやお父さんと離れて子どもたちだけで過ごす初めての機会!さて、この3日間で子どもたちはどのように成長したのでしょうか?見ていきましょう!
当日の様子
<食事・星空観察・プチ修行編>
食事作りに関しては健康福祉課の方々だけでなく、地域の婦人会からも応援に来てくださいました。数名の子は家でも料理のお手伝いをしているらしく、自信たっぷりに「家でも料理はしているからできるよ!」と頼もしい声も。半分以上の子は、家で料理のお手伝いをする機会がなく地域の方の手つきを見様見真似で・・・。少し手元がおぼつかない様子にソワソワしましたが、ゆっくりと上手に調理をしていました。

初日はどうすればいいか分からず、待つ時間も少し見られましたが、2日目には自分から出来たことを報告したり、どのようにしたらいいかを積極的に聞いて調理している様子が伺えました。
また、通学合宿では、短い時間ながらも星空観察やプチ修行体験が例年行われます。初日の星空観察では、隠岐しぜんむらの深谷治(ふかやはじめ)さんがお越しくださいました。

秋の星空は普段より見え易いとはいえども、変わりやすい島のお天気・・・ですが、この日はとても星が綺麗に見えました!外部から来た私にとっては、日頃から星が落ちて来そうなほど近く、沢山観え、本当に綺麗です。これが海士町の良さの一つであり、また子どもたちが故郷を感じられる瞬間になれば・・・と。星がないと物足りなさを感じるような。。。風物詩の一つだなと感じます。また、今回の星空観察を通じて知識を得ることでより自分の生まれた地域を身近に感じられたら・・・とふつふつと感じます。

最終日の朝には西方寺の住職である吉村栄典(よしむらたかのり)さんによるプチ修行にて、命の繋がりのお話や、物の捉え方のお話をしてくださいました。
なかでも「お寺での一番のお仕事は何だと思いますか?」と吉村さんの問いかけから始まったお話では「私たちの主な仕事は掃除です」と掃除の重要性や意義をお話をしてくださいました。
また、掃除のお話が子どもたちには大変響いたのか、隠岐開発センターに帰ってきてからの大掃除をみんな張り切って、声を掛け合いながらやってくれました。

今回のお話もそうですが、この3日間の経験を通じて普段自分がしていることや、家族の方がしてくれていることの意味や意義をより理解できたのではないでしょうか?
<3日間を通して>
毎日の恒例の振り返りタイム。しおりを活用して毎日出来たかどうかを記入しました。

三角だった項目が日に日に丸に変化していき、最終日の振り返りの時間には全部丸がついている子も!感想発表ではまだ人前で話すのが慣れないのか、恥ずかしそうに話す様子も観られましたが、一人一人それぞれきちんとたくさん感想を書くことができていました。すごい!
<通学合宿のその後・・・>
通学合宿では”ふるまい家庭生活プラスワン”と称して3日間で学んだことや体験したことを1週間、お家でも挑戦してみよう!という取り組みを行いました。親御さんからのコメントのなかには子どもたちがいなくて寂しかったというコメントも・・・寂しかったのは子供達だけではなかった様です。
また、習慣は3日間だけでは変わるものではありませんが、目に見えての変化は小さなものかもしれませんが、”自分のことを自分でしようとする姿勢があった”と意識の変化から”進んで家のお手伝いをしてくれた”など行動の変化も見られた様子。
なかでも親御さんが”子ども自身が出来ることを任そうと思った”など子供だけでなく親御さんの意識にも変化が・・・!この様に親子はお互いに成長していくのかなあとしみじみ感じました。
教育委員会のうらがわ
昨年度は形を変えて宿泊なしの”放課後ダッシュ村”として開催されましたが、今年度は宿泊も込みで無事開催されました。

通学合宿では、例年もらい湯をすることで地域の人との交流を図りますが、今年はひまわり(=海士町健康福祉センター)でお借りしました。

※もらい湯とは:地域の方の家に行き、風呂に入れてもらうこと
前回の普段の生活学校では大阪教育大学の学生さんたち(海士町の外部の人)が関わってくれましたが、今回は海士町に住む地域の方が携わってくださいました。普段の学校生活の参加者は中学3年生ということもあり、年齢の近い学生さんたちの刺激を受けながらこれからの自分の将来について考える機会になっていたように思いますが、今回はより地域の方と関わる中で、自分は自分1人ではなく、家族や周りの友達、地域の人たちに愛されて守られているのだと、感じてもらえていたら嬉しいです。
一言メモ
例年開催している”大人のお茶べり会”が通学合宿中に開催されました。親御さんたちは子どもたちとは別の部屋に集まって、交流会が行われます。小さな島といえど、少しずつ移住者が増えているからこそ、保護者さん同士が集まれるのも貴重な機会です。
また”大人のお茶べり会”の際中、子どもたちは食事の片付け・その後学習タイム。友達の兄弟とも仲良くきちんと共同作業。個人的にはその様子も海士町ならではの色が出ている気がします。

海士町では縦割り班を意識して学校で生活をします。中でも最高学年の6年生はいつも頼もしい姿を見せてくれて時には大人顔負け!下級生の子たちへの声かけも上手で、また5年生や4年生もそういう6年生のかっこいい姿を見て、自分たちもこんなかっこいい6年生になりたいと思いながら過ごします。人数が少ないからこそより密にできる関わりだなと感じます。

今回の通学合宿では、学校でお仕事をしている島体験生もスタッフとして参加してくれました。島体験生によると「学校ではない場所で、普段と違う事をするなかで、新たに見えた子どもたちの一面があった」そして、「学校生活においての子どもたちの意識の変化は大きくは見られないが、規則やルールに対して、なぜ守らないといけないのかについての質問が減った」と微笑みながら話してくれました。

この3日間の生活をしているなかで見えてくる等身大の自分。きっと出来なくてモヤモヤすることも、出来て嬉しかったこともたくさん経験出来たのではないかと思います。
学校でない自由な空間で子どもたちは何を表現するのか?「どうしてそれを守らないといけないの?」という質問が減ったのは、きっと自分たちの中で様々なことに意味があると少しでも考えられるようになったからだと思います。
文・山田若奈